「怖さのジャンルも色々」
怖い小説を総じて「ホラー小説」と言います。
しかし、怖いと思うものは人それぞれであるように、ホラー専門レーベルを見ても、テーマは色々。
ジャンルの定義を語るのは無粋なことですが、その違いを考えて、自分の書きたい「怖い話」が何であるのかを考えてみましょう。
「深層心理か血みどろか」
「怖い話」をジャンルに分けると、おおまかにこんな感じになります。
・「ホラー」読み手に戦慄を与える話のこと。
・「怪談」オバケや幽霊が出てくる話。日本古来のものを指す場合もあります。
・「オカルト」魔術や心霊現象が軸にある話のこと。
・「サイコ」精神病質の人物が出てくる話のこと。
・「スプラッター」猟奇的(血みどろ、ショッキング)な話のこと。
・「スリラー」読み手に緊張感や不安感(※主に恐怖や戦慄)を与える話のこと。
・「サスペンス」読み手に緊張感や不安感(※主に謎)を与える話のこと。
・「ミステリー」読み手に謎を解明する過程を見せる話のこと。
その他、ゾンビや吸血鬼が出てくるモンスター物や、とつぜん過酷な状況に追い込まれるパニック物、伝承や説話をベースにした民俗学的な物や伝奇小説など、一口に「怖い話」と言っても、これだけジャンルがあるのです。
「フォビアを知ろう」
初めて怖い話を書くとき、どうしても血飛沫の上がるショッキングなシーンを書いてしまいがちですが、大事なことは、読み手に「怖い!」と思わせることです。
確かに血飛沫ブシャァ! 内臓ドシャァ! も怖いですが、
では、そういったものを出さずに恐怖を描くには、一体どうしたらいいのでしょうか。
それは、フォビア(恐怖症)を巧みに使うことです。
フォビアにも色々ありますが、一般的に知られているものをあげてみましょう。
・「高所恐怖症(アクロフォビア)」落ちてしまいそうな不安感。
・「閉所恐怖症(クロストロフォビア)」息が詰まりそうな不安感。
・「暗所恐怖症(ナイクトフォビア)」目を開けているのに見えない不安感。
・「集合体恐怖症(トライポフォビア)」同形状のものが密集している嫌悪感(蓮コラなど)。
・「人形恐怖症(ペディオフォビア)」無機質な人形に、人の生(魂)を感じる不安感。
その他にも、虫が怖い、ピエロが怖い、尖った物が怖い、
不吉を暗示する数字(4・9・13・666)が怖いなど、フォビアは色々あります。
読み手の深層心理に迫って、怖い話を書いてみましょう。
「まとめ」
怖い話を書くときは、怖さの主軸にあるもの(ジャンル)と、
どういう恐怖(フォビア)を読み手に与えるかを考えましょう。
「人形恐怖症+オカルト」「閉所恐怖症+スリラー」「暗所恐怖症+サイコ」など、
組み合わせは無限大です。
個人的には「集合体恐怖症+都市伝説」が最恐です。
……ブツブツの塊が怖いです……。
この記事を書いた人


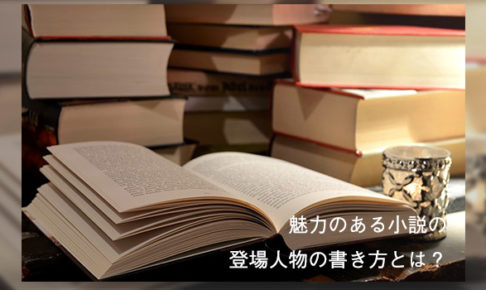
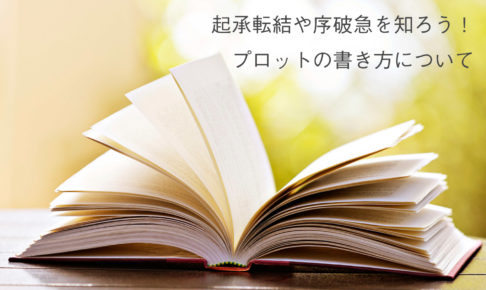






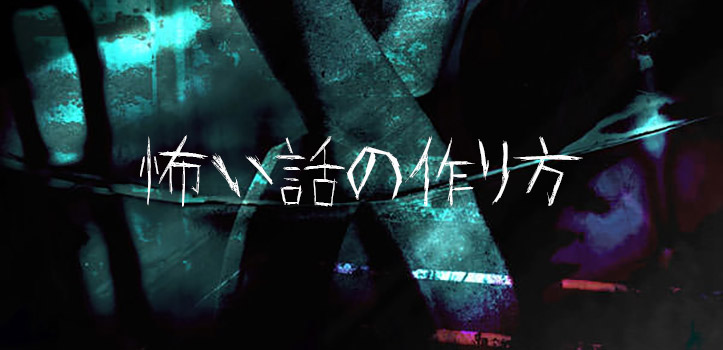



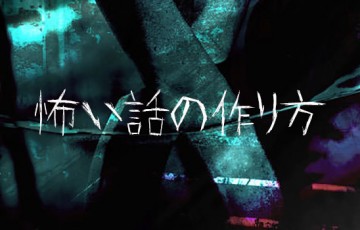
生活環境のせいか、比較的レトロジャンルが得意(な気がしている)。