「天才の基準」
「天才的な閃き」で謎のヒントを与えてくれたり、「天才的な才能」で主人公の行く手に立ちはだかったりと、天才キャラは、物語を大きく展開させる時に非常に便利な存在です。
しかし、安易な天才キャラの登場は、物語を希薄にさせてしまうもの。
「学校で一番○○な子」というレベルの天才なら特に問題はないですが、「大人顔負けの〜」とか「世界最高レベルの〜」という枕詞がつく天才になると、生半可なキャラ作りでは、読者も納得してくれません。
「天才であることの証明」
天才スポーツ選手や天才料理人など、天才キャラはたくさんありますが、厄介なのは頭脳派の天才キャラの描き方です。
IQの高さをアピールさせたり、危機的状況を思いつかない戦術で打破させたりと、読者に対し、あの手この手で「天才であることの証明」をしなければなりません。
しかし、これもバランスが大切です。
どうでもいいシーンで天才であることを誉めそやしたり、イージーな数値化で「IQ1000」のような天才設定をしてしまうと、天才というよりはむしろ馬鹿っぽく見えてしまいます(ギャグストーリーなら問題ありませんが)。
「天才に必要なもの」
では、どのようにすれば、「このキャラは天才である」と読者が理解してくれるのでしょうか。
天才キャラが一番輝いて見えるのは「何かが閃いたとき」です。
そして、そのために必要なのは「知識」です。
まずは、どのような知識を持った天才なのかを決めましょう。
そして作者は、その分野の専門書などを読んで、出来る限りの知識を集めましょう。
その知識をベースに危機的状況の打破などを行えば、天才キャラのIQの高さも不自然なものには見えなくなってくるはずです。
「まとめ」
作者が天才でなくても、天才のキャラは書けます。
ただし、キャラが天才であると見えるように、作者は知恵を絞らなければなりません。
作者の知恵と知識の相乗効果で、キャラは天才になっていくのです。
この記事を書いた人


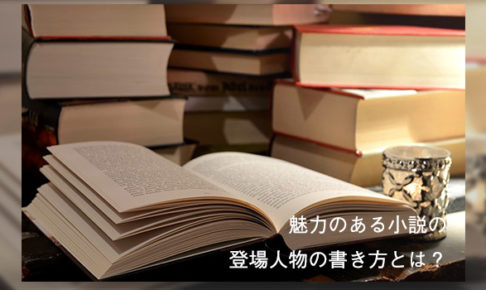
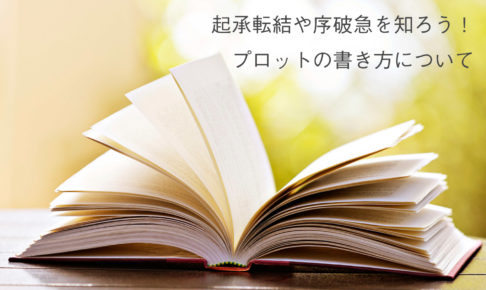






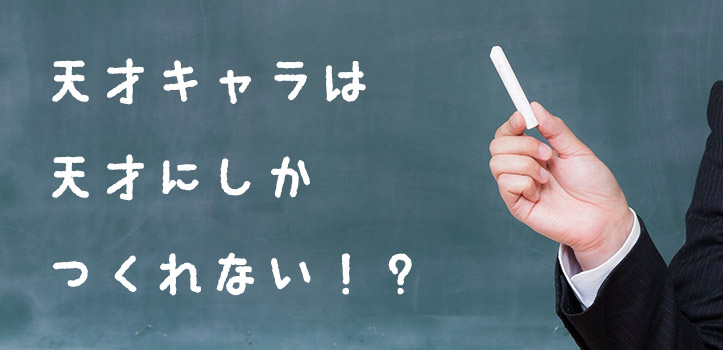



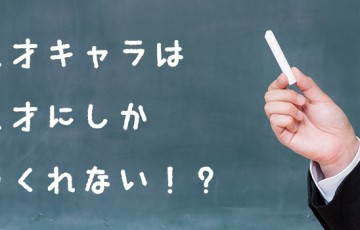
生活環境のせいか、比較的レトロジャンルが得意(な気がしている)。