「日本語はややこしい」
「おざなり? なおざり? この場合はどっちが正しいんだっけ?」
文章を書いていて、こんなことはありませんか?
・「おざなり」いいかげんに物事をすませること。(一応完遂)
・「なおざり」いいかげんにして放っておくこと。(完遂せず)
似ている言葉なのに、意味が違いますね。
そのほか、「姑息」という言葉も、「卑怯な」という意味で使っている人が多いですが、「姑」の意味は「しばらく」、「息」は「休む」を意味し、「しばらく休む=その場しのぎ」という意味で、けして卑怯ではありません。
「変化する言葉」
【私は彼女に向かって、「おたんこなす!」と言った。】
……さて、この文章のおかしなところが分かりますか?
諸説ありますが、一説によると、「おたんこなす」を漢字で書くと「御短小茄子」になるそうです。
これは、吉原の遊女が嫌いな客に対して使っていた隠語で、男性器を馬鹿にして「たんちんぼう」と言っていたのが「おたんちん」となり、その後、「おたんこなす」に変化したのだと言われています。
と言うことは、もともと男性器のない女性に向かって「おたんこなす」と言うのは、大きな間違いということになりますね。
ところが、「おたんこなす」は「御炭鉱茄子」、つまり、炭鉱近くで採れた茄子は売り物にならないことが語源、という説もあるのです。
こちらの意味ですと、性別は特に関係ないということになります。
じゃあ「書き手」が「御炭鉱茄子」のつもりで使ったのなら問題ないじゃん、と思われがちですが、実はこれが問題なのです。
私たち「書き手」は、「読み手」がどちらの説を知っているのか、知る術がないからです。
読み手が「御短小茄子派」だったときのことを考えて、やはり女性に対して使う言葉に「おたんこなす」は避けたほうがいいでしょう。
こういう複数の語源を持つ言葉って、実は他にもたくさんあります。
「困ったときは辞書を引く!」
○○という言葉を使いたいけど、誤用と言われそう。
でも、誤用の方がメジャーなのに……。
そんなときは、類語辞典を引きましょう。
同じ意味の違う言葉が、きっと見つかるはず。
読み手を混乱させないためにも、誤用の見本になりやすいような言葉は、あえて使用しないほうがいいでしょう。
「まとめ」
普段から、分からない言葉や、意味があやふやな言葉に遭遇したら、面倒くさがらずに辞書を引く癖を付けましょう!
当たり前のことですが、かなり大事なことですよ!
この記事を書いた人


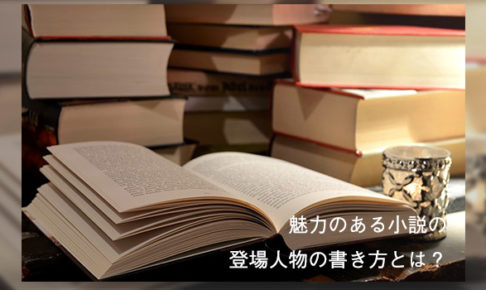
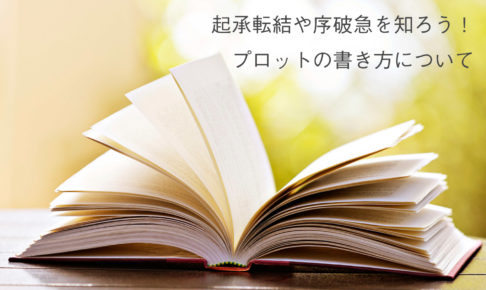






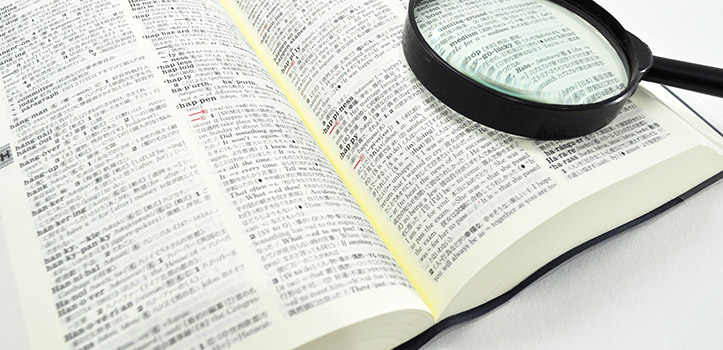



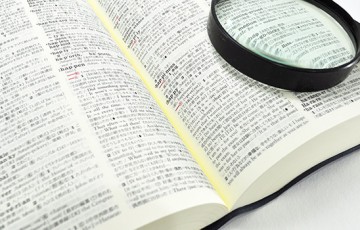
生活環境のせいか、比較的レトロジャンルが得意(な気がしている)。