食わず嫌いしない
読書でも執筆でも言える事ですが、同じジャンルにこだわらない方がいいです。
これは特に知識のインフローとなる読書で言える事かもしれません。
著作名は伏せますが、某ミステリー系文学賞を獲った作品のレビューを見ていると「面白いんだけど既視感がある」といった記述がありました。
言われてみればそうだなと思ったのですが、この作者さんはもしかしたらミステリー小説ばっかり読んでいたのかも分かりません。
一応その方の名誉を傷付けないように言っておきますが、その作品は十分面白かったし、次回作も読みたいと感じましたので悪しからず。
大きな影響を及ぼす”読書遍歴”
言うまでもありませんが、書き手の作風に対して、彼の読書遍歴というのは大きな影響を及ぼします。
極端な例を挙げると、翻訳小説ばっかり読んでいると本当に翻訳調の文体になってしまいます。
それで怖いのが、特定の作家ばかり読んでいると、当然そのバッタもんを書く危険性が増えるという事です。
同じ相撲部屋の力士が先輩力士の技を盗むのと同じですね。
まあ、これがスポーツの世界で、且つちゃんと結果さえ出していれば大して批判はされないんですが、芸術系の分野ではそうはいきません。
○○のコピーというレッテルを貼られ続けるのはなかなか屈辱的だと思いますよ。
それを避けるには、なるべく多岐に渡る作品を読むしかないですね。
それぞれの作品からちょっとずつ影響を受けるなら、吐き出した作品に「誰かのコピー感」は遥かに無くなると思います。
どうせ誰からも影響を受けないなんて端から無理なのですから、たくさんの本を読んで良い刺激を受ければいいわけです。
執筆中のジャンルと違うジャンルの本を読む
また、この理論は執筆中の心構えに敷衍して考える事が出来ます。
当然の事ながらSFばっかり読んでSF小説を書いたら、誰かの作品に似てしまうのは当たり前です。そりゃそうです。
そういう場合は、執筆中のジャンルとはまるで違う話を読みまくると良いですね。
ホラー小説を読んだり恋愛モノを読んだり、案外全然関係ない分野に創作のヒントは眠っているものです。
斬新な創作物というのは、今までの常識では考えられない組み合わせから生まれる事が多いです。
そういう場合、新ジャンルの創始者は大体ゲテモノ扱いされるわけですが、既存の常識をひっくり返すのが創作家の仕事ですから、そこはガマンするしかないですね。
文句を言ってるだけの評論家は歴史には残れないんです。
仮に斬新さを追求するわけではないにしても、食わず嫌いで全然読まないジャンルの小説があるという事はあなたの個性を一つ殺した事になります。
それは非常に勿体無い。
読んだ本は全部自分の血肉にするぐらいじゃないと、貪欲さが足りないというものですよ。
色んな本を読んで、色んな滋養を吸収しましょう。
動画投稿者様


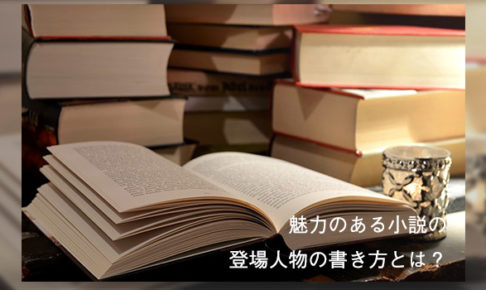
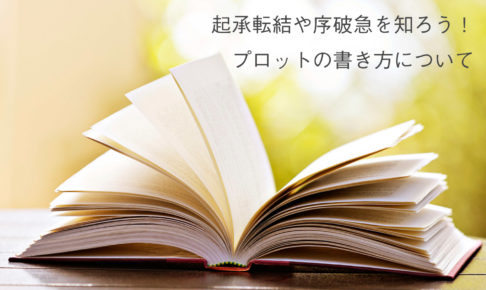






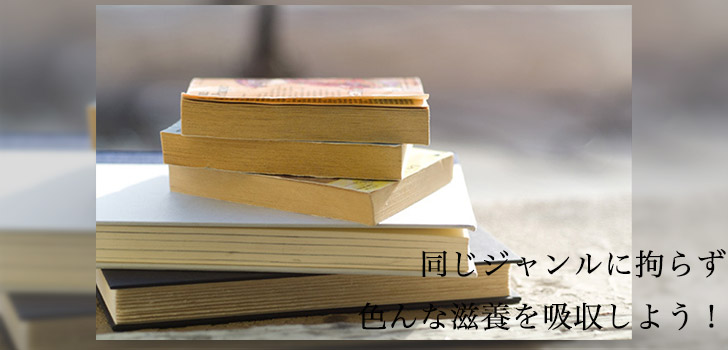



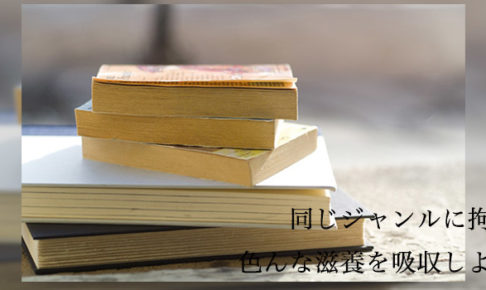
電子書籍界隈を中心に活動するインディーズ作家で元プロボクサー。リングでボコボコにされている内に、拳で闘うよりもペンで闘う方が向いている事に気付き作家に転身。無駄な体力をフル活用しつつ、自由かつ斬新な小説を模索している。