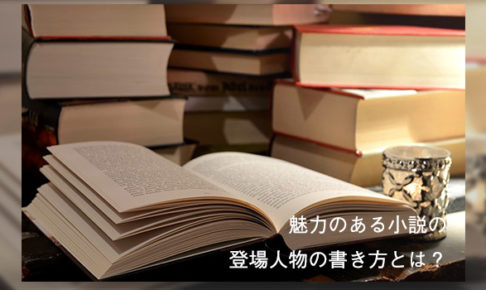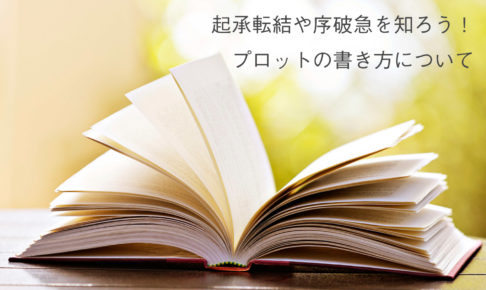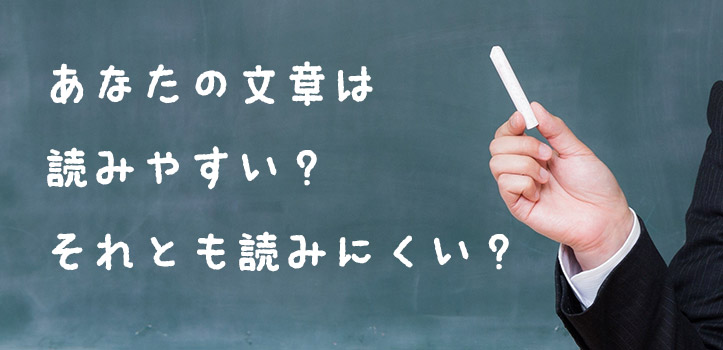二つを決める要素とは?
個人差はあれど、文章には読みやすいものと読みにくいものがありますよね。
それではこの二つを決める要素とは一体何なのでしょうか。
例えば言葉の意味。
普段使い慣れていない言葉を使われていると文章の意味がわからず、読みにくい文章になってしまいます。
けれどこれは知識という個人的な問題です。
それでは大抵の人にとって読みやすい・読みにくいを決める要素とは何なのでしょう。
それはずばり、テンポです。
例文を出してみましょう。
以下例文
彼はようやく用件を思い出したのだった。
彼は例の件について喋った。
「……………」
すると彼の友人はこう言った。
「……………」
彼が大口を開けて笑った。
「……………」
気付けば二人揃って笑っていた。
彼はようやく用件を思い出したのだった。
彼は例の件について喋った。
「……………」
すると彼の友人はこう言った。
「……………」
彼が大口を開けて笑った。
「……………」
気付けば二人揃って笑っていた。
いかがでしょう。
〜だった、〜た、〜いた、という過去形の繰り返しに加え、地の文→台詞→地の文……の繰り返しにもなっています。
なんだか全体的に単調ではないでしょうか。
それでは先ほどの文を読みやすく改善してみましょう。
以下例文
彼はようやく用件を思い出したので、例の件について喋った。
「……………」
すると彼の友人がこう言ったものだから、彼は大口を開けて笑う。
「……………」
「……………」
気付けば二人揃って笑っていた。
彼はようやく用件を思い出したので、例の件について喋った。
「……………」
すると彼の友人がこう言ったものだから、彼は大口を開けて笑う。
「……………」
「……………」
気付けば二人揃って笑っていた。
改善したのは地の文を過去形のみにしない点、台詞を連続にした点です。
この方が読みやすく、テンポも良いと思いませんか?
少し考えつつ時制を改めたり組み替えたりするだけで読みやすさがぐっと変わるのです。
台詞にも応用?
また、読みやすさの話とはちょっと変わるかもしれませんが、文字の表記を変えることで誰が喋っているのかわかりやすいようにすることもできます。
例えば「僕」という一人称。
これをカタカナ・平仮名にしてみます
「ボクは……」
「ぼくは……」
どうでしょう。
なんだか、幼い子が喋っているような印象がしませんか?
例えそうでなくとも、たくさん登場人物が出てきて一人称が似通っているときは、それぞれ人物の性格や年齢を加味した上で表記を変えてみましょう。
そうすることで読者にも誰が喋っているのか、少しでもわかりやすくなるのではないでしょうか。
この本では、数々のベストセラーのライティングを担当し、ライトノベルを100作品以上もリライトしてきた著者が実践している方法のすべてが明かされています。
わかりにくい文の例を挙げ、どこをどう変えればわかりやすい文になるのか、また、人を惹きつける文にする秘訣は何かを解説していきます。
わかりにくい文の例を挙げ、どこをどう変えればわかりやすい文になるのか、また、人を惹きつける文にする秘訣は何かを解説していきます。
by amazon
この記事を書いた人

物理と数学が天敵の工学部生。漫画アニメゲーム全般大好きで、毎期ごとに増える嫁が悩みの種です