イマジネーションを膨らませる言葉
作品が一つ出来上がって、「さて新作のネタを創るぞー!」と思ったとき、ふと何も思い浮かばなくて困ったことはありませんか?
そんなときは、お題に挑戦してみましょう。
ネットで検索すると、診断メーカーやジェネレーターサービス、それにお題配布サイトなど、便利なものがたくさんあります。
そこから抽出した言葉を基にして、作品のイメージを大きく広げてみましょう。
配布されたお題の問題点
新作を書き出す際にとても便利な「お題」ですが、まったく問題がない訳ではありません。
当たり前のことですが、各サービスやサイトごとに利用規約があり、その規約を守らなければ、お題を利用することができないのです。
つまり、どれだけ素晴らしい作品ができたとしても、発表媒体や利用方法が規約違反に当たれば、作品はお蔵入りとなってしまうのです。
そんな事態にならないよう、サービスに書かれた利用規約をきちんと読み、理解したうえでお題を使用しましょう。
お題じゃないものをお題にする
基本的に、ネットで配布されたお題は商業作品に使えません。
そこで、私が商業作品を書く際に利用するのが、万葉集や古今和歌集です。
では、どのように使うのか、具体例を挙げてみましょう。
【あかねさす 日並べなくに わが恋は 吉野の川の 霧に立ちつつ】
意味:「(吉野に来てから)まだそんなに月日が経っていないのに、私の恋心は吉野川の霧のように立ち上っている」
遠距離恋愛の歌ですね。では、イメージを広げてみましょう。
1.どうして遠距離恋愛になったのか
×転勤 ×転校 ○進学
2.二人はどういう関係か①
×同僚 ○幼馴染 ×同級生
3.二人はどういう関係か②
×両思い ×片思い ○両思いだけど擦れ違い
4.どうして恋心が立ち上っているのか
○ライバル登場 ×寂しい ×プロポーズしたい
ちょっとベタですが、これでベースができました。
これに「あかね」や「川」や「霧」をヒントに様々なイベントシーンを肉付けして、一つの物語を作っていくのです。
まとめ
ネタが見つからなくても、焦る必要はありません。
ああでもない、こうでもないと頭を悩ませているうちに、意外なところからポンと出てきたりするものですよ。
プロの作家が、何を観察して、それをどうやってストーリーに仕上げてゆくのか、その舞台裏を見せながら、具体的な指導でストーリーを書けるように導きます。
この記事を書いた人


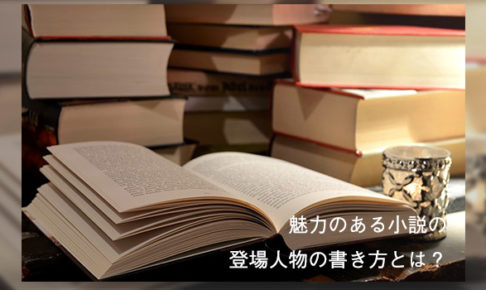
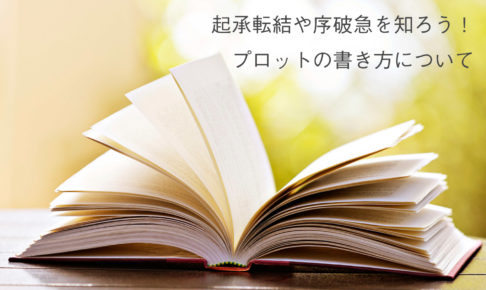











生活環境のせいか、比較的レトロジャンルが得意(な気がしている)。