「学校じゃ教えてくれない日本の文化」
時代劇ドラマが少なくなって久しいですが、再放送があれば、ついつい観てしまう時代劇。
本屋に行けば、いまだに江戸の町を舞台とした小説は人気が高く、同心、与力に岡っ引きなどについては、大体の方がご存知だと思います。
では、吉原遊郭についてはどうでしょうか。
花魁や太夫は聞いたことがあるし、映画やドラマでも観たことがあるけど、詳しいことは知らない。
だって、教科書にも載ってないし、先生も教えてくれなかったから。
そういう方が多いのではないでしょうか。
書いてみたいけど、よく分からない吉原遊郭について、少しだけご説明したいと思います。
「吉原遊郭って、どんなとこ?」
時代劇ドラマや小説の中に、女性が身を売る場所として「吉原遊郭」と「岡場所」が出てきますよね。
では、「吉原遊郭」と「岡場所」の違いは分かりますか?
実は、幕府公認の歓楽街が「吉原遊郭」で、非公認の歓楽街が「岡場所」なのです。
幕府公認というだけあって、「吉原遊郭」では、お客にも厳しいマナーが求められます。
花魁とあんなことやこんなことをしたい! と思っても、いきなり出来る訳ではありません。
まずは顔合わせをし、二回目で少しだけ話をして、三回目にようやく「お客」として相手をしてもらえるのです。
そして最上級の花魁ともなれば、こちらからお客を選ぶ事だって出来ます。
しかも、「今日は気分が乗らないので、さっさと帰ってください」なんてことも言ったり出来るのです。
「岡場所」は、吉原より断然お手頃でカジュアルな歓楽街(なにせ非合法ですから)。
マナーもそこまで問われません。
吉原と岡場所は、似て非なる場所なのです。
ただし、吉原遊郭の中にも、大見世・中見世・小見世・切見世などのランクがあって、下のランクの見世でしたら、それほどマナーを求められなかったりもします。
「ありんす国とは言いますが」
吉原遊郭の遊女と言えば、思い出すのが「ありんす」という独特な言葉です。
これは廓詞(くるわことば)や里詞(さとことば)と言われ、この言葉遣いから、吉原は「ありんす国」と呼ばれることもありました。
しかし、全ての語尾に「ありんす」を用いたわけではありません。
各妓楼によって方言のように廓言葉が違っていたり、他にも「おす」「ざんす」「なんし」「ざます」等が存在していました。
「実は長い歴史を持つ吉原遊郭」
吉原遊郭には、「元吉原」と「新吉原」が存在します。
「元吉原」は、江戸幕府開設間もない1617年、日本橋に誕生しました。
その後、明暦の大火で消失、日本橋から浅草に移転したのが「新吉原」です。
時代劇に出てくる「吉原」は、比較的こちらの「新吉原」の方が多いでしょう。
そして吉原遊郭は、1957年(昭和32年)の売春防止法の施行と共に姿を消しました。
これだけ長い歴史を持つ吉原ですから、お客の様子や遊女のファッションも大きく変化しています。
同じ江戸時代でも、「元吉原」と「新吉原」じゃ全然違うんですよ。
「まとめ」
一口に「吉原」と言っても、時代やランクによって様々な遊女達。
物語に登場させるときは、時代やストーリーに沿うように、きちんと調べて書くことをおすすめします。
この記事を書いた人


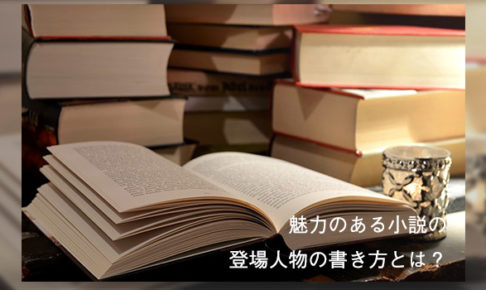
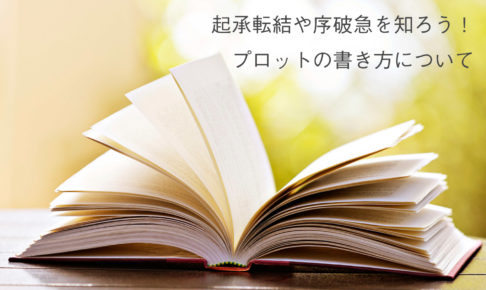












生活環境のせいか、比較的レトロジャンルが得意(な気がしている)。